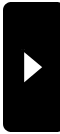2008年07月16日
大人がしっかりせんとなあ
今日、少年によるバスジャック事件が起きましたね。事件を起こしたのが中学2年生と聞いて、自分の息子と同年齢なので、とても心を痛めています。
今の社会に何が起こっているのか?ニュースを見れば、痛ましい事件ばかり。しかも、少年による猟奇的な事件も少なくないことに驚かされます。
18世紀の思想家ルソーが書いた「エミール」の中で
「子どもを不幸にする確実な方法はいつでも何でも手に入れられるようにしてやることだ」とあります。
ある大学の先生は物が豊かになった80年代から、子ども達は急速に思いやりを失い、他人に頼ることを必要にしなくなり、モラルを失った社会の縮図と調査から話しています。その調査は、中高生に歩いている時に人が倒れたということを想定してそれにどのような行動を取るかと意識調査をしたところ、半数はどうしていいかわからず何もしないというものでした。
そう言えば、秋葉原の殺傷事件の時、倒れている人達を平気で携帯の写真に撮るという無神経な人が多かったことにも憤りというか、悲しくなってしまいますね。
やはり、何かが狂ってるおかしな時代なんだと思うのです。物や情報が豊かになったけど人との繋がりが希薄な分だけ心が育つ機会が失われているのかもしれません。
自分のエゴを押し通す結果、お金で自分の子どもを先生にしてしまう大人が本当に子どもたちに何を教えていけるのか!悲しい時代です。
大人がしゃんとできんと、子どもはもっとしゃんとできんよなあ~。。。。

今の社会に何が起こっているのか?ニュースを見れば、痛ましい事件ばかり。しかも、少年による猟奇的な事件も少なくないことに驚かされます。
18世紀の思想家ルソーが書いた「エミール」の中で
「子どもを不幸にする確実な方法はいつでも何でも手に入れられるようにしてやることだ」とあります。
ある大学の先生は物が豊かになった80年代から、子ども達は急速に思いやりを失い、他人に頼ることを必要にしなくなり、モラルを失った社会の縮図と調査から話しています。その調査は、中高生に歩いている時に人が倒れたということを想定してそれにどのような行動を取るかと意識調査をしたところ、半数はどうしていいかわからず何もしないというものでした。
そう言えば、秋葉原の殺傷事件の時、倒れている人達を平気で携帯の写真に撮るという無神経な人が多かったことにも憤りというか、悲しくなってしまいますね。
やはり、何かが狂ってるおかしな時代なんだと思うのです。物や情報が豊かになったけど人との繋がりが希薄な分だけ心が育つ機会が失われているのかもしれません。
自分のエゴを押し通す結果、お金で自分の子どもを先生にしてしまう大人が本当に子どもたちに何を教えていけるのか!悲しい時代です。
大人がしゃんとできんと、子どもはもっとしゃんとできんよなあ~。。。。


2008年07月03日
当たり前のこと
本当に今日は蒸し暑い一日でしたね。
 さて、今日は息子のPTAがありました。
さて、今日は息子のPTAがありました。
授業参観とその後の学級懇談とあるのですが、なかなか残る人もクラスの半分ほどでした。

懇談の中で話題になったのは、子ども達の最近の様子や友達関係のことでした。
子どもの言葉遣いや友達とのコミュニケーションの取り方などを気にされている方が多いようです。
これは、社会の流れともリンクしているようで、やはり子育てのキーワードには必ず「子どものコミュニケーション能力」がでてきます。
子どもの個々の知識や運動能力が優れていたとしても、それを生かした「自己の達成感」や世の中に対する「役立ち感」というのは、他の人との関わりなしでは実現するのは難しいことのように思えます。
子ども達には、多くの人と係わり合い、相手の思いと自分の思いとを重ね合える人に成長して欲しいものです。。。
そして、この場は「日常の中」にあるのも忘れてはいけないことだと思います。
当たり前のように毎日、きちんと3食を食べることができ、当たり前のように学校に行き、勉強して遊ぶことができる。
当たり前のように花壇に花が植えてあり、当たり前のようにトイレのスリッパが揃えてあり、当たり前のように本の整理がついている。
この「当たり前のこと」にもっと目を向けることから、子ども達は学ぶことは多いように思います。
ずいぶん前に「世界がもし100人の村だったら」という本が爆発的に売れました。
当時、数字があやふやとか偽善的という意見もありましたが、私はこの本で各々が何かを考えるきっかけを手にできたかということの方が大切なのではないかと思います。数字の根拠があやふやであっても、現実に戦争や紛争は起こり、小さい子どもも含む多くの人達が毎日不条理に死んでいます。
これが当たり前の現実なのです。今の子ども達にも、自分の置かれた現実がいかに幸せであり、そして、当たり前が何かを考えることから始めて欲しいと思うのです。
You Tubeで分かりやすい動画を見つけました。興味のある方は見てね


 さて、今日は息子のPTAがありました。
さて、今日は息子のPTAがありました。授業参観とその後の学級懇談とあるのですが、なかなか残る人もクラスの半分ほどでした。

懇談の中で話題になったのは、子ども達の最近の様子や友達関係のことでした。
子どもの言葉遣いや友達とのコミュニケーションの取り方などを気にされている方が多いようです。
これは、社会の流れともリンクしているようで、やはり子育てのキーワードには必ず「子どものコミュニケーション能力」がでてきます。
子どもの個々の知識や運動能力が優れていたとしても、それを生かした「自己の達成感」や世の中に対する「役立ち感」というのは、他の人との関わりなしでは実現するのは難しいことのように思えます。
子ども達には、多くの人と係わり合い、相手の思いと自分の思いとを重ね合える人に成長して欲しいものです。。。
そして、この場は「日常の中」にあるのも忘れてはいけないことだと思います。
当たり前のように毎日、きちんと3食を食べることができ、当たり前のように学校に行き、勉強して遊ぶことができる。
当たり前のように花壇に花が植えてあり、当たり前のようにトイレのスリッパが揃えてあり、当たり前のように本の整理がついている。
この「当たり前のこと」にもっと目を向けることから、子ども達は学ぶことは多いように思います。
ずいぶん前に「世界がもし100人の村だったら」という本が爆発的に売れました。
当時、数字があやふやとか偽善的という意見もありましたが、私はこの本で各々が何かを考えるきっかけを手にできたかということの方が大切なのではないかと思います。数字の根拠があやふやであっても、現実に戦争や紛争は起こり、小さい子どもも含む多くの人達が毎日不条理に死んでいます。
これが当たり前の現実なのです。今の子ども達にも、自分の置かれた現実がいかに幸せであり、そして、当たり前が何かを考えることから始めて欲しいと思うのです。
You Tubeで分かりやすい動画を見つけました。興味のある方は見てね


2008年06月17日
空気と関係
今日は朝からちょっとだけPTAのお仕事で学校へ。そこでもらった、PTAの通信の中に家の子の学校の教頭先生が書いたコラムが書いてあるので紹介いたします。
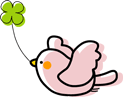
 『昨年来、「K.Y」や「そんなの関係ね~」という言葉が流行りだした。流行に敏感な子ども達のこと、これは流行りだすなと思いつつ子ども達の様子を見ていると、案の定、授業中にこれらの言葉を発する子どもがいた。
『昨年来、「K.Y」や「そんなの関係ね~」という言葉が流行りだした。流行に敏感な子ども達のこと、これは流行りだすなと思いつつ子ども達の様子を見ていると、案の定、授業中にこれらの言葉を発する子どもがいた。
これはチャンスと見て、早々これらの言葉について考える機会をもった。
問いは「人を『K.Y』=『場の空気を読めない?』で済ませていいのか?」「人の話を『そんなの関係ない』で済ませていいのか?」である。
子ども達からは具体的な生活場面での話が出て大いに盛り上がった。そして出された結論は、「今は何をしなければならないときか、何が行われようとしているときか(=目的)」を考えた行動が大切で「K.Y」と「そんなの関係ね~」は、とてもわがままな行動だということになった。
子ども達には、誰でも認める場の空気を創り、積極的に関係を創る人になってもらいたいです。
本当にその通りだと思います。流行語に惑わされることなく、人との交流の中で暖かな空気を持てたり、人と多くの関係を結んでいくことの方がずう~っと大事なことだと思います。
子ども達がコミュニケーションをうまく取れなくなったという声は実際に子ども達と向き合ってる専門家の間でも指摘されていることです。そして、突き詰めると必要なのは言語能力ではないかと思うのです。
先ずは親が、そして大人が地域社会が子ども達とコミュニケーション能力を培う場所(機会)を増やしてあげることではないかと思います。
文部科学省が出した新学習指導要領に「生きる力を育むことを目指し」とあります。
生きる力・・・・やはり、人との関係なしでは生けていけないのではないでしょうか。人を認めて、いろんな人との関係を結ぶコミュニケーション能力は子ども達にとって、「生きる力」のひとつなのです。
そう思うと、子ども達をもう無視できませんよね。 もっと子どもと話さないとと思うでしょ。まずは我が子や知り合いの子から話すことから・・・・このご時勢、不審者と思われないようにしましょうね(笑)
もっと子どもと話さないとと思うでしょ。まずは我が子や知り合いの子から話すことから・・・・このご時勢、不審者と思われないようにしましょうね(笑)
空気と関係、生きていくのにやっぱり必要ですねえ~。

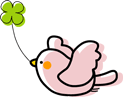
 『昨年来、「K.Y」や「そんなの関係ね~」という言葉が流行りだした。流行に敏感な子ども達のこと、これは流行りだすなと思いつつ子ども達の様子を見ていると、案の定、授業中にこれらの言葉を発する子どもがいた。
『昨年来、「K.Y」や「そんなの関係ね~」という言葉が流行りだした。流行に敏感な子ども達のこと、これは流行りだすなと思いつつ子ども達の様子を見ていると、案の定、授業中にこれらの言葉を発する子どもがいた。これはチャンスと見て、早々これらの言葉について考える機会をもった。
問いは「人を『K.Y』=『場の空気を読めない?』で済ませていいのか?」「人の話を『そんなの関係ない』で済ませていいのか?」である。
子ども達からは具体的な生活場面での話が出て大いに盛り上がった。そして出された結論は、「今は何をしなければならないときか、何が行われようとしているときか(=目的)」を考えた行動が大切で「K.Y」と「そんなの関係ね~」は、とてもわがままな行動だということになった。
子ども達には、誰でも認める場の空気を創り、積極的に関係を創る人になってもらいたいです。
本当にその通りだと思います。流行語に惑わされることなく、人との交流の中で暖かな空気を持てたり、人と多くの関係を結んでいくことの方がずう~っと大事なことだと思います。
子ども達がコミュニケーションをうまく取れなくなったという声は実際に子ども達と向き合ってる専門家の間でも指摘されていることです。そして、突き詰めると必要なのは言語能力ではないかと思うのです。
先ずは親が、そして大人が地域社会が子ども達とコミュニケーション能力を培う場所(機会)を増やしてあげることではないかと思います。
文部科学省が出した新学習指導要領に「生きる力を育むことを目指し」とあります。
生きる力・・・・やはり、人との関係なしでは生けていけないのではないでしょうか。人を認めて、いろんな人との関係を結ぶコミュニケーション能力は子ども達にとって、「生きる力」のひとつなのです。
そう思うと、子ども達をもう無視できませんよね。
 もっと子どもと話さないとと思うでしょ。まずは我が子や知り合いの子から話すことから・・・・このご時勢、不審者と思われないようにしましょうね(笑)
もっと子どもと話さないとと思うでしょ。まずは我が子や知り合いの子から話すことから・・・・このご時勢、不審者と思われないようにしましょうね(笑)空気と関係、生きていくのにやっぱり必要ですねえ~。

タグ :コミュニケーション
2008年06月04日
子は宝
ベビーマッサージを学んで、子どもにとってスキンシップがいかに大切かを改めて感じています。
たくさん、抱っこされたり触られた赤ちゃんは、とても穏やかで体や心の成長も安定します。
これは、近年科学的にも証明されていて、いろんな研究がなされています。スキンシップを受けている子は、受けない子よりも泣く回数が少なく、寝つきもよいこともわかっています。
抱いてもらえる、泣いたらあやしてもらえるそう安心していられる赤ちゃんは周囲を観察し情報を吸収する余裕があり、脳の発達にも大いに関係しているとも研究結果が出ているのです。
そして、スキンシップをすることにより親や保護者と子どもの間には、強い絆が生まれることは何よりもかけがえのないことです。
700年以上前、神聖ローマ帝国の皇帝が「話し声や子守唄を聞かないで育った子どもはどんな言葉を話すのか」という実験を行ったそうです。
数人の赤ちゃんを乳母に預けて、最低限の世話だけをさせ、抱っこや愛撫はさせずに育てました。すると、赤ちゃんは全員、言葉を話す前に死んでしまったそうです。
皇帝の愚かな実験が示しているのは、人間の成長に不可欠な要素はいつの時代にも変わらないということ。
素晴らしい可能性に満ちた子ども達に愛情をたっぷりと注いであげること、それが何よりも大切なように思えるのです。
しかし、愛情を受けたくても受けられない子ども達も多いという現実。そのことも知っておかなければならないってこと。
だから我が子をしっかりと愛してあげられて、そして他人の子どものことも愛してあげられるようになったら、もっと社会は豊かになるだろうなあ~っと思うのです。
昔も今も、やっぱり子は宝なんですよね~。子どもが心豊かに育ってもらわんと、老後は不安だらけやでぇ~。(なしか、ここだけ大分弁。。。 )
)
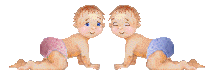
 6月6日(金) 9:30に栄光園に伺う予定です。
6月6日(金) 9:30に栄光園に伺う予定です。
マッサージのお出来になる方、マッサージは無理だけど抱っこボランティアだったらという方sakura先生か私にメールかブログのメッセージでご連絡ください。栄光園までの地図をお送りします。車のない方もご連絡ください。
 「愛のもみもみ軍団募集」
「愛のもみもみ軍団募集」
乳児院や養護施設などにいる赤ちゃんや幼児へのマッサージや長く寝たきりの方やお年寄りの方へのハンドや足のマッサージを病院や施設などを訪問、マッサージをしてくださるボランティアの方を募集します。
マッサージはsakura先生が指導いたします。
今後も会員を増やしたいと思いますので練習用人形、オイルなど経費がかかります。
ボランティアの志をお持ちの方に申し訳ないのですが実費¥3,000のみ
負担お願いいたします。活動前に少なくても6時間以上の講習を受講して
赤ちゃんにマッサージしてもいいレベルになってからの参加になります。
申し訳ありませんがお子様連れの参加はできません。
年齢は問いませんが子どもたちを愛しんでくださる方、大歓迎です。
我が子にベビーマッサージをしたいからという理由での
講習会の参加は固くお断りいたします。
ボランティアは登録制で活動日時がいろいろになると思いますので
ご自分が参加できる時に自由参加してください。
場所 大分市内 sakura先生宅(JR滝尾駅近く)
6月7日(土)13:00~14:30
6月10日(火) 13:00~14:30
小桑さん宅(週刊小桑/ご厚意ににひたすら感謝です)別府の方はこちらへ
6月13日(金)13:00~14:30
10号線沿いの餅が浜のマルショクに13:00集合です
興味のある方は左記のsakura先生にメールでメールアドレスをお送りください
詳細と地図をお送りします。
子どもたちは優しい、温かいあなたの手を求めています


たくさん、抱っこされたり触られた赤ちゃんは、とても穏やかで体や心の成長も安定します。
これは、近年科学的にも証明されていて、いろんな研究がなされています。スキンシップを受けている子は、受けない子よりも泣く回数が少なく、寝つきもよいこともわかっています。
抱いてもらえる、泣いたらあやしてもらえるそう安心していられる赤ちゃんは周囲を観察し情報を吸収する余裕があり、脳の発達にも大いに関係しているとも研究結果が出ているのです。
そして、スキンシップをすることにより親や保護者と子どもの間には、強い絆が生まれることは何よりもかけがえのないことです。
700年以上前、神聖ローマ帝国の皇帝が「話し声や子守唄を聞かないで育った子どもはどんな言葉を話すのか」という実験を行ったそうです。
数人の赤ちゃんを乳母に預けて、最低限の世話だけをさせ、抱っこや愛撫はさせずに育てました。すると、赤ちゃんは全員、言葉を話す前に死んでしまったそうです。

皇帝の愚かな実験が示しているのは、人間の成長に不可欠な要素はいつの時代にも変わらないということ。
素晴らしい可能性に満ちた子ども達に愛情をたっぷりと注いであげること、それが何よりも大切なように思えるのです。
しかし、愛情を受けたくても受けられない子ども達も多いという現実。そのことも知っておかなければならないってこと。
だから我が子をしっかりと愛してあげられて、そして他人の子どものことも愛してあげられるようになったら、もっと社会は豊かになるだろうなあ~っと思うのです。
昔も今も、やっぱり子は宝なんですよね~。子どもが心豊かに育ってもらわんと、老後は不安だらけやでぇ~。(なしか、ここだけ大分弁。。。
 )
)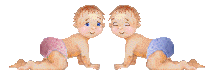
 6月6日(金) 9:30に栄光園に伺う予定です。
6月6日(金) 9:30に栄光園に伺う予定です。マッサージのお出来になる方、マッサージは無理だけど抱っこボランティアだったらという方sakura先生か私にメールかブログのメッセージでご連絡ください。栄光園までの地図をお送りします。車のない方もご連絡ください。
 「愛のもみもみ軍団募集」
「愛のもみもみ軍団募集」
乳児院や養護施設などにいる赤ちゃんや幼児へのマッサージや長く寝たきりの方やお年寄りの方へのハンドや足のマッサージを病院や施設などを訪問、マッサージをしてくださるボランティアの方を募集します。
マッサージはsakura先生が指導いたします。
今後も会員を増やしたいと思いますので練習用人形、オイルなど経費がかかります。
ボランティアの志をお持ちの方に申し訳ないのですが実費¥3,000のみ
負担お願いいたします。活動前に少なくても6時間以上の講習を受講して
赤ちゃんにマッサージしてもいいレベルになってからの参加になります。
申し訳ありませんがお子様連れの参加はできません。
年齢は問いませんが子どもたちを愛しんでくださる方、大歓迎です。
我が子にベビーマッサージをしたいからという理由での
講習会の参加は固くお断りいたします。
ボランティアは登録制で活動日時がいろいろになると思いますので
ご自分が参加できる時に自由参加してください。
場所 大分市内 sakura先生宅(JR滝尾駅近く)
6月7日(土)13:00~14:30
6月10日(火) 13:00~14:30
小桑さん宅(週刊小桑/ご厚意ににひたすら感謝です)別府の方はこちらへ
6月13日(金)13:00~14:30
10号線沿いの餅が浜のマルショクに13:00集合です
興味のある方は左記のsakura先生にメールでメールアドレスをお送りください
詳細と地図をお送りします。
子どもたちは優しい、温かいあなたの手を求めています

2008年04月28日
やんちゃな子を持つ友達の悩みは・・・。
2歳になる家の姉の子どもは、言葉の発達も著しい!会うたびに、いろんな言葉をしゃべれるようになっているわけで、近頃はみんなに「ふ~んだ!」とか「あっちに行って!」だとか可愛気のないことも言うので私もたじたじなのです。
やっぱり、男の子より女の子の方がませてる感じがしますね。


友達の子どもはもうすぐ3歳でやんちゃ盛り。友達の悩みは、もっぱら汚い言葉(おちんちんやお尻やうんこ・・・etc)を連発することなのだそうです。 そう言えば、うちの子もそんな時期があったなあ~。。
そう言えば、うちの子もそんな時期があったなあ~。。
偉い学者さんによると、これは子どもの発達のごく普通な一段階なのであまり気にすることはないとあります。また、感情や認知能力の発達にも関係しているんだとか。
子どもの言語能力が急速に発達する時期はトイレのしつけの時期と重なるので自分の身体に興味がいくのは自然なことなのだそうです。
では、どうして連発して言うのかというと・・・・言葉の意味はわからなくても、親が驚いたりいつもと違うリアクションというのはわかるので何度も繰り返して面白がっているんですよね。
肝心なのは親が笑ったり(子どもはますます調子にのって連発するよね。 )あわてないことで、親が無視すれば多くの場合、その種の言葉は言わなくなるようです。
)あわてないことで、親が無視すれば多くの場合、その種の言葉は言わなくなるようです。
また、少し大きくなって理解できるようになると、「それは、人前では言わない言葉なのよ」などと簡潔にさりげなく不適切だと悟らせることも効果的なようです。
まあ~成長段階の一つだと思って、むやみに怒るよりも無視するほうがいいみたいですね。
うちの子もそんなやんちゃでおゃべりな時代があったのが、とても懐かしい。。。
なぜならば、近頃はめっきり口数が減った長男!はい、少し反抗期に入っております。なんだかなあ~。。。。
やっぱり、男の子より女の子の方がませてる感じがしますね。



友達の子どもはもうすぐ3歳でやんちゃ盛り。友達の悩みは、もっぱら汚い言葉(おちんちんやお尻やうんこ・・・etc)を連発することなのだそうです。
 そう言えば、うちの子もそんな時期があったなあ~。。
そう言えば、うちの子もそんな時期があったなあ~。。偉い学者さんによると、これは子どもの発達のごく普通な一段階なのであまり気にすることはないとあります。また、感情や認知能力の発達にも関係しているんだとか。
子どもの言語能力が急速に発達する時期はトイレのしつけの時期と重なるので自分の身体に興味がいくのは自然なことなのだそうです。
では、どうして連発して言うのかというと・・・・言葉の意味はわからなくても、親が驚いたりいつもと違うリアクションというのはわかるので何度も繰り返して面白がっているんですよね。
肝心なのは親が笑ったり(子どもはますます調子にのって連発するよね。
 )あわてないことで、親が無視すれば多くの場合、その種の言葉は言わなくなるようです。
)あわてないことで、親が無視すれば多くの場合、その種の言葉は言わなくなるようです。また、少し大きくなって理解できるようになると、「それは、人前では言わない言葉なのよ」などと簡潔にさりげなく不適切だと悟らせることも効果的なようです。
まあ~成長段階の一つだと思って、むやみに怒るよりも無視するほうがいいみたいですね。

うちの子もそんなやんちゃでおゃべりな時代があったのが、とても懐かしい。。。
なぜならば、近頃はめっきり口数が減った長男!はい、少し反抗期に入っております。なんだかなあ~。。。。

タグ :子育て
2008年02月28日
食育って。
昨日、朝カレーのことについて書いたのですが、今日たまたま出かけた先で知り合いにあい、いろいろと食の話になりました。
彼女は、この2年間「食育」のことを勉強して食育指導員の資格を取ったそうで、とても興味深い話を聞くことができました。
そもそも「食育」という言葉。Wikipediaによると「様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること」とあります。 単なる料理に関する教育ではなく、人が健全に生きていく上で、正しい食生活を送るための知識を持つということだと思います。平成17年には、「食育によって国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことを目的とする」食育基本法が成立されています。
さて、彼女が一番力を入れているのは子ども達の食の問題です。食育でしばしば出てくる問題に「コショク」という言葉があります。この「コショク」には3つの漢字が当てられるそうです。
家族と一緒であってもそれぞれが別のものを食べる、もしくはそれぞれの部屋で食べることを指す「個食」
一人で食事をする、特に子どものみで食事することを指す「孤食」
同じものばかりを食べ続ける事を指す「固食」だそうです。
なんだか寂しさが漂う「コショク」です。これらの現象の大きな要因は家族の団欒が減っている現代の家庭事情にあるようです。
仕事を続ける女性が増えていて家事にさける時間が少なくなったり冷凍食品、レトルト食品などの普及や中食(なかしょく)と呼ばれる持ち帰り惣菜店の増加などで、家庭での調理が減っている…などといわれています。
ううう・・・・ちょっと心当たりがあるので、聞いていてビミョーな気分になったのですが・・・。
子ども達が健全に育っていくには、まずは食事を考えることからはじめよう!としっかり、アドバイスされました。
暇な時に子どもと一緒に料理を作ったり、食事や料理について話すことから家庭での食の見直しが大切のようですね。
う~ん、奥深いなあ~「食育」!!

彼女は、この2年間「食育」のことを勉強して食育指導員の資格を取ったそうで、とても興味深い話を聞くことができました。
そもそも「食育」という言葉。Wikipediaによると「様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること」とあります。 単なる料理に関する教育ではなく、人が健全に生きていく上で、正しい食生活を送るための知識を持つということだと思います。平成17年には、「食育によって国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことを目的とする」食育基本法が成立されています。
さて、彼女が一番力を入れているのは子ども達の食の問題です。食育でしばしば出てくる問題に「コショク」という言葉があります。この「コショク」には3つの漢字が当てられるそうです。
家族と一緒であってもそれぞれが別のものを食べる、もしくはそれぞれの部屋で食べることを指す「個食」
一人で食事をする、特に子どものみで食事することを指す「孤食」
同じものばかりを食べ続ける事を指す「固食」だそうです。
なんだか寂しさが漂う「コショク」です。これらの現象の大きな要因は家族の団欒が減っている現代の家庭事情にあるようです。
仕事を続ける女性が増えていて家事にさける時間が少なくなったり冷凍食品、レトルト食品などの普及や中食(なかしょく)と呼ばれる持ち帰り惣菜店の増加などで、家庭での調理が減っている…などといわれています。
ううう・・・・ちょっと心当たりがあるので、聞いていてビミョーな気分になったのですが・・・。

子ども達が健全に育っていくには、まずは食事を考えることからはじめよう!としっかり、アドバイスされました。
暇な時に子どもと一緒に料理を作ったり、食事や料理について話すことから家庭での食の見直しが大切のようですね。
う~ん、奥深いなあ~「食育」!!

タグ :食育
2008年02月09日
ノミのはなし

驚異的な“ジャンプ力”で知られるノミを知っていますよね。
成虫は体長1mmから4mmほどの小ささで体は、髪や毛の間を動きやすいように出来ています。
ノミは最大で垂直方向に20cm(体長4mmとして体長の50倍)水平方向に41cm(同100倍)跳ぶことが出来ると言われています。(もし身長160cmの人間が同じように跳ぶことが出来たら80m、幅跳びなら160m跳べることになるそうですよ!
 )
)それでは、20cm跳べるノミがいます。そのノミを高さ10cmの箱に入れ、ふたをします。
そしてしばらく放置しておきます。その間、箱の中で、ノミは跳び続けます。
それから、そのノミを再び箱から出してみるとそのノミはどうなると思いますか?
A.跳べなくなる B.また20cm跳ぶ C.箱の中のストレスから開放され、40cm跳べるようになっている D,疲れているから跳ばない E.すでにノミではない

実は、これらどれも不正解なのです。
正解は、 「10cmしか跳べなくなっている」そうです。箱の中でふたをされていたため、10cmしか跳ぶことのできなかったノミは
箱から出されても、10cmしか跳べなくなるのです。

20cm跳ぶ能力を持っているにもかかわらず、こうなってしまうのはなぜでしょうか。
それは、「箱の中」という環境で、「10cm」という壁をつくられてしまったために、「10cm」が、自分に跳べる高さの限界と思ってしまったからなのだそうです。
自分で勝手に限界をつくってしまったために、本来持っている能力を発揮できなくなってしまったのです。
これは、私達人間にも同じことが起こりうるのではないでしょうか。私には無理だ。こんなことできるわけがない。
その思いが自分の限界だと感じ先にはすすめなくなる。
今までの経験や、今置かれている環境で自分自身に限界をつくってしまうことってあるような気がします。
また、子ども達にも子どもだからこれは無理だろうと決め付けてしまうこともあるかもしれません。
でも、心の持ちようでいくらでも伸びていく可能性を誰にでも持っているのかもしれません。

小さなノミの話でも大きな何かに気づかせてくれたような気がしますね。

タグ :ノミの話
2008年01月09日
与えすぎること

お正月休みが終わった子ども達と久しぶりのサークルでした。

みんなお正月の話やお年玉の話で最初はテンションが上がりっぱなしでした!

ほんと、今の子ども達ってお年玉を結構もらっていて、その使い道もいろいろですね。
一番多いのはやはり、ゲームやゲームソフト。それから、本やおもちゃと欲しいものはクリスマスからお正月にかけて手に入る子どもにとっては夢のような時期なんですよね。(羨ましい!!)
物が豊かで本当に恵まれていると時代だと思います。

でも、こんな話をちょっと思い出しました。だいぶ前に、あるお母様から聞いたことなんですけど、当時小学2年生の次男がリモコンカーのカタログに夢中になっていました。
そこに載っている車のことは全部覚えていて、いろいろと人にリモコンカーについてうんちくを言うことも好きだったようです。
でも、その子は一度も「リモコンカーが欲しい!」と言うことはなかったし友達から借りてやるようなこともなかったそうです。
恐らく、カタログを眺めるのが好きな段階だったのでしょうね。ところが、しばらくたって両親が子どもを喜ばせようとリモコンカーを買ってしまったそうです。しかも、ちょっと値がはる結構、いいものだったそうです。
結局、そのリモコンカーは1度動かしただけで使うことも無く今でも押入れの中に眠っているそうです。

恐らく、子どもはリモコンカーそのものが欲しいわけではなかったんですね。ただ、眺めていることが好きだったんでしょう。
もしかすると、もう少したって興味が出たかもしれません。しかし、子どもが一度も欲しいと言わないのに、喜ぶだろうと買い与えてしまった、これは親の失敗です。そのお母さんも、先回りして何でも買うことはよくないことだと反省していました。
今の時代、欲しいものがあればあまり我慢しなくてもすぐ手に入るような風潮にあります。子どもが喜ぶから、我慢させるのはかわいそうだからと言って何でも与えることは、「豊かさ」が子どもをダメにしていく落とし穴のような気さえします。
物を大切にすることをせず、物を欲しがる一方の子どもがそこから育ってしまうかもしれないと言う事を親は忘れてはいけないような気がします。子どもよりも大人が考えなおさなければならないことが多いような気がしますね。
さて、お年玉をいっぱい貰った子ども達、「貯金もちゃんとしているよ」って報告してくれる子も多くて感心!感心!
んん・・・・でもちょっと待った!!ちゃっかり欲しいゲームなどは買ってるってことは、貯金できるくらいたくさん貰っているってことなのね。。。。

きっと、今の私よりもお金持ちに違いない!!


誰か私に貢ぐ君もしくは貢ぐちゃん、いない???やっぱり、いないよねえ。。。。

2007年10月19日
知りたい気持ちを育てる
子どもも高学年や中学になってくると、勉強も難しくなってきます。(実際、長男の数学を教えるのに限界を感じていますが。。。 )
)
だんだんと勉強も高度になり、本人自身のやる気が大きく成績を左右してきます。この時、学んでいることへの興味がわかなければ、当然やる気も起りません。そのやる気の基となるのが知的好奇心だそうです。
知的好奇心とは、簡単に言うと知りたいという心の欲求で、本来誰にでももっているものですが、その欲求の強さに差が生じているようです。
どうしてそのような差ができるのかは、子どもが「なぜ?」と聞いてきた時のお母さんの対応の仕方で差ができるという説があります。
3,4歳の頃は「なぜ?なぜ?時期」と言われるように、子どもがお母さんによく質問をしてきます。だいたい、小学校の低学年ぐらいまで質問を投げてきます。
この時こそ、子どもの知的好奇心が高まっている時期なのです。その時に答えるのが面倒だったり、忙しいからあとでと言って、子どもの質問を封じたりすると、芽生えてきた知的好奇心はしぼんでしまうことになるのだそうです。その繰り返しが知りたいという気持ちが乏しい子どもになってしまうのです。
子どものなぜにできるだけ答えてあげることが子どもの知りたいという気持ちを育てることに繋がっていきます。
私もできるだけ、子どもの質問には答えてあげられるようにしています。どうしても、分からない時は正直に分からないといいます。そして、本や辞典で(今なら、パソコンなどで)一緒に調べてみたりします。
その時間が親子のコミュニケーションの時間になったり、また調べる手段を教える時間になったりします。
子どものなぜは知りたい気持ちを高めるよい機会。上手に答えてあげられるといいですよね!


 10月20日( 土)のサークルのお知らせ
10月20日( 土)のサークルのお知らせ
 湯布院子どもえいごサークル
湯布院子どもえいごサークル
第3土曜日はお休みです!!
 小国子どもえいごサークル
小国子どもえいごサークル
10月20日のみ 時間変更になっています!!ご注意下さい!
幼児・小学生とも 15:00~15:40
小国子ども英語サークルご案内 入会費、教材費なしの一回 参加費 1200円
入会費、教材費なしの一回 参加費 1200円
☆場所: 小国町 蓮台寺 (熊本県阿蘇郡小国町宮原2172番地)
大塚石油(九州石油)・石田商店前
☆日時: 第1・第3 土曜日(月2回) 1回 40分レッスン
*日程は天候、または都合により変更される場合があります
小学生こども英語サークル
①小学生 (小1~小3) 14:30~15:10
②小学生 (小4~小6) 14:30~15:10
親子英語サークル
◎幼児 3歳~5歳 14:30~15:10
*幼児クラスは親子参加。小学生は子どものみ参加可。
*レッスンは予約制です。また、見学もOKです!!
左記のオーナーにメールでお問い合わせください。
 )
)だんだんと勉強も高度になり、本人自身のやる気が大きく成績を左右してきます。この時、学んでいることへの興味がわかなければ、当然やる気も起りません。そのやる気の基となるのが知的好奇心だそうです。
知的好奇心とは、簡単に言うと知りたいという心の欲求で、本来誰にでももっているものですが、その欲求の強さに差が生じているようです。
どうしてそのような差ができるのかは、子どもが「なぜ?」と聞いてきた時のお母さんの対応の仕方で差ができるという説があります。

3,4歳の頃は「なぜ?なぜ?時期」と言われるように、子どもがお母さんによく質問をしてきます。だいたい、小学校の低学年ぐらいまで質問を投げてきます。
この時こそ、子どもの知的好奇心が高まっている時期なのです。その時に答えるのが面倒だったり、忙しいからあとでと言って、子どもの質問を封じたりすると、芽生えてきた知的好奇心はしぼんでしまうことになるのだそうです。その繰り返しが知りたいという気持ちが乏しい子どもになってしまうのです。
子どものなぜにできるだけ答えてあげることが子どもの知りたいという気持ちを育てることに繋がっていきます。
私もできるだけ、子どもの質問には答えてあげられるようにしています。どうしても、分からない時は正直に分からないといいます。そして、本や辞典で(今なら、パソコンなどで)一緒に調べてみたりします。
その時間が親子のコミュニケーションの時間になったり、また調べる手段を教える時間になったりします。
子どものなぜは知りたい気持ちを高めるよい機会。上手に答えてあげられるといいですよね!



 10月20日( 土)のサークルのお知らせ
10月20日( 土)のサークルのお知らせ 湯布院子どもえいごサークル
湯布院子どもえいごサークル第3土曜日はお休みです!!
 小国子どもえいごサークル
小国子どもえいごサークル10月20日のみ 時間変更になっています!!ご注意下さい!
幼児・小学生とも 15:00~15:40
小国子ども英語サークルご案内
 入会費、教材費なしの一回 参加費 1200円
入会費、教材費なしの一回 参加費 1200円 ☆場所: 小国町 蓮台寺 (熊本県阿蘇郡小国町宮原2172番地)
大塚石油(九州石油)・石田商店前
☆日時: 第1・第3 土曜日(月2回) 1回 40分レッスン
*日程は天候、または都合により変更される場合があります
小学生こども英語サークル
①小学生 (小1~小3) 14:30~15:10
②小学生 (小4~小6) 14:30~15:10
親子英語サークル
◎幼児 3歳~5歳 14:30~15:10
*幼児クラスは親子参加。小学生は子どものみ参加可。
*レッスンは予約制です。また、見学もOKです!!
左記のオーナーにメールでお問い合わせください。
2007年09月09日
納得できる生き方
9月に入って毎日、子ども達は運動会の練習に励んでいます。体操服は真っ黒で汗だくで戻ってきます。
今月の終わりはいよいよ運動会です。運動会が近づくと思い出す話があるのです。
それは、ある小さな山の小学校で勤めていた先生の話なのですが、ここで載せることにしました。
運動会が近づくと思い出す光景があります。まだ山の小さな小学校に勤めていた頃の話です。
プログラムの最後、高学年二十余名による一輪車リレーでのことです。白組がゴールを決めた直後に赤組のアンカーが出発しました。一周遅れでトラックを回らなければなりません。
たいていのこどもは照れるか、ふてくされてしまうが彼女は違ってました。バトンを受けるなり、猛スピードでダッシュしてたった一人でも力一杯の走りを見せてくれました。疾風のごとく走り抜けゴールを過ぎやっと止まったのです。
負けは出発前から決まっています。彼女は勝ち負けで走ったのではありません。勝負などを超えた走りでした。みんながいつでも一等にはなれない。それを思うとき、彼女の姿を思い出すのです。
自分で納得できる生き方ができればいいんだと。
勝った白組のアンカーは思い出せないけど、ただ一人負けのレースをひた走る彼女の姿は、記憶の中で今も輝いているのです。
情景がすぐ目の前に浮かぶような気がしました。彼女は勝つことはできないけど、一生懸命走ることは決して無駄ではないことを知っている強い子なんだと思います。
私達は生きていく間、様々な壁に当たります。その壁から逃げ出すよりも回り道でも、遅くても乗り越えることは、自分を一つ成長させるのです。
私は、一生懸命頑張ることに無駄なことはなに一つないと思うのです。きっと、いつかそれは自分のために実を結ぶと思っています。
頑張って自分が納得できるなら、勝負がどうであれ気持ちは満ち足りているんですよね。 彼女はそう教えてくれました。
子ども達の運動会では秋空の下、一生懸命頑張る子ども達の姿を想像しながら、私も力一杯、エールを送ろうと思ってます。




今月の終わりはいよいよ運動会です。運動会が近づくと思い出す話があるのです。
それは、ある小さな山の小学校で勤めていた先生の話なのですが、ここで載せることにしました。

運動会が近づくと思い出す光景があります。まだ山の小さな小学校に勤めていた頃の話です。
プログラムの最後、高学年二十余名による一輪車リレーでのことです。白組がゴールを決めた直後に赤組のアンカーが出発しました。一周遅れでトラックを回らなければなりません。
たいていのこどもは照れるか、ふてくされてしまうが彼女は違ってました。バトンを受けるなり、猛スピードでダッシュしてたった一人でも力一杯の走りを見せてくれました。疾風のごとく走り抜けゴールを過ぎやっと止まったのです。
負けは出発前から決まっています。彼女は勝ち負けで走ったのではありません。勝負などを超えた走りでした。みんながいつでも一等にはなれない。それを思うとき、彼女の姿を思い出すのです。
自分で納得できる生き方ができればいいんだと。
勝った白組のアンカーは思い出せないけど、ただ一人負けのレースをひた走る彼女の姿は、記憶の中で今も輝いているのです。
情景がすぐ目の前に浮かぶような気がしました。彼女は勝つことはできないけど、一生懸命走ることは決して無駄ではないことを知っている強い子なんだと思います。
私達は生きていく間、様々な壁に当たります。その壁から逃げ出すよりも回り道でも、遅くても乗り越えることは、自分を一つ成長させるのです。
私は、一生懸命頑張ることに無駄なことはなに一つないと思うのです。きっと、いつかそれは自分のために実を結ぶと思っています。
頑張って自分が納得できるなら、勝負がどうであれ気持ちは満ち足りているんですよね。 彼女はそう教えてくれました。
子ども達の運動会では秋空の下、一生懸命頑張る子ども達の姿を想像しながら、私も力一杯、エールを送ろうと思ってます。




2007年08月20日
親の姿・診断書

大分県警察本部少年課が出してる「子どもを問題児に育ててしまうかも?」父母の姿・診断表というものがあります。
項目が長いのでそのうちの20項目だけここで紹介いたします。子育ての参考になればと思います。
 1.困難や不安を先々に片付けたり、泣く手段に負けて手助けしてやる親。
1.困難や不安を先々に片付けたり、泣く手段に負けて手助けしてやる親。 2.小さな成功を大きく褒め、自信をつけさせ次の挑戦に導いてやれない親。
2.小さな成功を大きく褒め、自信をつけさせ次の挑戦に導いてやれない親。 3.小さな努力を他児や兄弟との比較や大人の価値観で評価する親。
3.小さな努力を他児や兄弟との比較や大人の価値観で評価する親。 4.自然体験や遊びを通じた友達とのふれあい体験の機会を奪っている親。
4.自然体験や遊びを通じた友達とのふれあい体験の機会を奪っている親。 5.親の自己満足だけで習い事を無理強いし、子どもの時間を奪っている親。
5.親の自己満足だけで習い事を無理強いし、子どもの時間を奪っている親。 6.他の親との子育て競争に熱中し、子どもに成長をせかしている親。
6.他の親との子育て競争に熱中し、子どもに成長をせかしている親。 7.「○○すると○まるに叱られるよ」などと、叱り方を他人に任せている親。
7.「○○すると○まるに叱られるよ」などと、叱り方を他人に任せている親。 8.感情的な体罰などで子どもの恐怖心をあおったり、くどくどと怒る親。
8.感情的な体罰などで子どもの恐怖心をあおったり、くどくどと怒る親。 9.なぜ叱られたのか理解させないまま、後始末もさせない親。
9.なぜ叱られたのか理解させないまま、後始末もさせない親。 10.叱ってくれた他人に感謝しない親。
10.叱ってくれた他人に感謝しない親。 11.我慢を経験させないで、機嫌取りで物を買い与える親。
11.我慢を経験させないで、機嫌取りで物を買い与える親。 12.子どもの前で学校不信・担任不信を口にし、共同歩調を取れない親。
12.子どもの前で学校不信・担任不信を口にし、共同歩調を取れない親。 13.自分の都合で社会のマナーや規則を破ってみせる親。
13.自分の都合で社会のマナーや規則を破ってみせる親。 14.他人に対するあいさつや感謝の気持ちを自ら表現できない親。
14.他人に対するあいさつや感謝の気持ちを自ら表現できない親。 15.他人に対する憎しみ、けなし、いじめの言葉を子どもに聞かせる親。
15.他人に対する憎しみ、けなし、いじめの言葉を子どもに聞かせる親。 16.子どもとのふれあいよりも自分の遊び・楽しみを最優先させる親。
16.子どもとのふれあいよりも自分の遊び・楽しみを最優先させる親。 17.暗い人生しか語れず、活力の感じられない親。
17.暗い人生しか語れず、活力の感じられない親。 18.片方の親の言動を否定し、子どもを見方に付けようとする親。
18.片方の親の言動を否定し、子どもを見方に付けようとする親。 19.片方の親をなじるなど、夫婦関係の不仲を子どもに気づかれている親。
19.片方の親をなじるなど、夫婦関係の不仲を子どもに気づかれている親。 20.「親に感謝しなさい」と言いつつ、自分の父母を大切にしない親。
20.「親に感謝しなさい」と言いつつ、自分の父母を大切にしない親。 2007年08月16日
イギリスのしつけ


マガジンALCで興味深い記事を見つけました。

それは、イギリスのしつけについての記事です。イギリスと言えば、しつけにしても厳しいとされています。
伝統的にアッパークラス(上流階級)やアッパーミドル(上位中流階級)の裕福な家(いずれもわたしン家には無縁ですなあ
 )では、ナニー(nanny)と呼ばれる住み込みの教育係りを雇い食事の仕方や話し方、社交のマナーなどを厳しく教えていたそうです。
)では、ナニー(nanny)と呼ばれる住み込みの教育係りを雇い食事の仕方や話し方、社交のマナーなどを厳しく教えていたそうです。しかし、今の時代、自由に子どもを伸び伸びと育てようとする人も増えてきて、同時に子どもが言う事を聞かないと嘆く若い親も増えてきました。

そこは、イギリスだけではなく日本でもそうですよねえ~!!
そこで登場したのが「Supernanny」というテレビ番組だそうです。子育てに悩む家庭を訪問して子育て方を伝授するという番組でイギリスでは人気番組の一つになっているようです。
最近では、日本でもそのイギリスのナニー的子育てがウケているようですが、その中の しつけ5か条 を記します。
1.規則正しい生活をさせるべし
2.大人の会話を中断させるべからず
3.しかるときは毅然と褒めるときは思い切り
4.だれが権力(authority)をもつかを知らしめるべし
5.「境界」をあたえるべし
5の「境界」?と思う方も多いでしょうが、スーパーナニーに言わせると「自由奔放にさせると子どもは不安になる。境界線を与える事によって子どもは安心感を覚えて、遊びや勉強に集中でき、お行儀よくなり親の言う事も聞くようになる」そうです。
(上の5か条の3・4.5って、犬のしつけにもよ~く似てると思うのですが。。。。。
 )
)お国が違っても、子育てには共通なところは多いはず。いろんな考え方を知ってみるのもいいですよね!!

2007年07月05日
「疲れた」こどもたち
先日見た、雑誌に最近すぐに「疲れた」と言うこどもが増えていると載っていました。
確かに、英語のレッスンをしている時、小学校でも「疲れる」とか「めんどくさい」と言う言葉をよく耳にします。椅子に座っている時、背もたれに寄りかかったり、ほおずえをついたりする子も少なくはありません。また、立たせると壁にすぐもたれたり、ふらふらしたりする子もいます。

これは、単に子ども自身の問題ではなく大人の私達がそうさせているのではないかとも記事にはありました。
「人は生まれていきなり"人間”になるんじゃない。子どもが”人間になるためにはある程度の条件や環境が必要なのに、それを奪っているのが今の社会じゃないか」と言った人がいます。
「子どもが育つ条件」とは、自然、社会、文化の3つの環境だそうです。でも、自然は破壊され、こどもの遊び場はほとんどないのが現状で社会環境も大きく変化しています。
かつての、「家庭」は親子で畑の仕事などをする「生活の場」でした。
子どもは生活の労働のなかで様々なルールや秩序を覚えていきます。
また、子どもができない事を大人がすることで子どもは尊敬の念を抱き、礼儀も生まれてきました。
子どもと大人の境界線があったのです。生産の場である家庭は教育の場であり親は子に経験や知識、生きる力やルールを自然に見せていました。
しかし、今の家庭は、食事をして様々なものを消費する消費の場になっているといいます。
消費社会は、大人にとっては快適かもしれないけど子どもにとって人間としての基本的な能力を養うことが難しい社会になったのかもしれません。
楽を求めるあまり、子ども達の心や体までも怠け者にしているのは大人社会の大きなツケなのかもしれませんね。


確かに、英語のレッスンをしている時、小学校でも「疲れる」とか「めんどくさい」と言う言葉をよく耳にします。椅子に座っている時、背もたれに寄りかかったり、ほおずえをついたりする子も少なくはありません。また、立たせると壁にすぐもたれたり、ふらふらしたりする子もいます。


これは、単に子ども自身の問題ではなく大人の私達がそうさせているのではないかとも記事にはありました。
「人は生まれていきなり"人間”になるんじゃない。子どもが”人間になるためにはある程度の条件や環境が必要なのに、それを奪っているのが今の社会じゃないか」と言った人がいます。
「子どもが育つ条件」とは、自然、社会、文化の3つの環境だそうです。でも、自然は破壊され、こどもの遊び場はほとんどないのが現状で社会環境も大きく変化しています。

かつての、「家庭」は親子で畑の仕事などをする「生活の場」でした。
子どもは生活の労働のなかで様々なルールや秩序を覚えていきます。
また、子どもができない事を大人がすることで子どもは尊敬の念を抱き、礼儀も生まれてきました。
子どもと大人の境界線があったのです。生産の場である家庭は教育の場であり親は子に経験や知識、生きる力やルールを自然に見せていました。
しかし、今の家庭は、食事をして様々なものを消費する消費の場になっているといいます。
消費社会は、大人にとっては快適かもしれないけど子どもにとって人間としての基本的な能力を養うことが難しい社会になったのかもしれません。
楽を求めるあまり、子ども達の心や体までも怠け者にしているのは大人社会の大きなツケなのかもしれませんね。


2007年07月02日
気が済むまでやらせてみる
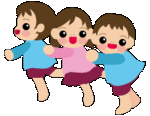
子どもが漫画やテレビをずーっと見ていて、なかなか勉強に取り組まないとき、どうしますか?
たいていは、漫画を取り上げたりテレビを見るのを禁止したりとしませんか。
ただこの方法は、一時的には親の言うことを聞いて勉強をしますが、いつもいつも禁止してばかりだとよくないそうです。
なぜなら、人間は禁止をされると余計に欲するという天邪鬼(あまのじゃく)的心理傾向を持っているからなのだそうです。
禁止された子どもは親の目を盗んで漫画やテレビを見るようになり漫画やテレビに強い執着を持つようになる恐れがあるからです。
確かに、私も子どもの頃ダメと言われると余計にしたくなるタイプでした。

そこで、思い切り漫画を読ませたりテレビを見せたりとする逆行することも一つの方法だそうですよ。
イギリスやアメリカで行われている”オープン・システム”という教育法があるそうです。遊びと勉強をすべて子どもの自主性に任せてしまいます。遊びも勉強も本人次第の環境の中では当然、遊びだけを優先させ勉強を後回しにする子も大勢います。
ところが、いざ勉強をする時には、驚くほどの集中力を発揮し遊んではダメと言われながら勉強した子どもたちよりもよい成績をあげているそうです。
自らの行動を自分の判断で決定させることが次の作業の意欲を高め子どもは集中力を発揮するのだそうです。

いつもいつも、これをしてはダメと禁止で管理することは賢明ではなく、ある程度子どもの自主的な判断に任せた方がよい場合もあるということですね。
そう言えば、うちの子も何も言わない時の方が、勉強の取り組み方が早かったり、終わらせるのもそんなに時間がかからなかったりします。

そろそろ、自主的に行動を任せた方がいい時期なのかもしれませんね~。

2007年06月28日
ロジカル・シンキング
『論理的思考』のことをロジカルシンキングと言うのですが、要するに物事を筋道を立てて考えるということです。
私は、この筋道を立てて話すこと はあまり得意ではありません。
最近こそは、人前で話をする機会も多く、だいぶ話すこと自体には慣れてきたのですが、まだまだ要領よく順番に説明する事には苦労しています。
最近読んだ育児書にも、小さな頃からこのロジカル・シンキングを育てることはコミュニケーションをとる上で、抵抗なくスムーズにできる方法の一つだと書いてありました。
その第一歩は、とにかく子どもに話をさせる機会を多く持たせることだそうです。言葉を、子どもから奪わないことだそうです。
例えば、子どもが親に何かを話したい時「忙しいから後でね。」なんて言っていませんか?
例えば、子どもが質問をされたのに親の方が先回りをして、子どもの名前や年などを先に言ってませんか?
自由に話をさせたり説明をさせたりすることで子どもは言葉を学んでいるのです。その学ぶ機会を親が奪っていることも多いようですね。
そして、単語で言葉を返すよりも、親もたくさんの言葉をそえて話しかけることが子どもの語彙を広げ、想像力も働くようになるそうです。
 「りんごが美味しそうだね。」と言うよりも「赤くてきれいなりんごだね。きっと、食べると甘くて美味しいだろうね。」という方が子どもの頭にはイメージがはっきりとできるのです。
「りんごが美味しそうだね。」と言うよりも「赤くてきれいなりんごだね。きっと、食べると甘くて美味しいだろうね。」という方が子どもの頭にはイメージがはっきりとできるのです。
その積み重ねが、ロジカル・シンキングができるようになるのだそうです。そして、話す事が好きになり物事を理解することも早くなるのだそうですよ。
そして、大人にとっても誰かに話すことはストレス解消にも心のリハビリにもなるそうです。
そうですよね!!話すだけでも気分がすっきりとなること多いですもの。 私もいっぱい話す事にしようっと!!(話しすぎってか?
私もいっぱい話す事にしようっと!!(話しすぎってか? )
)

私は、この筋道を立てて話すこと はあまり得意ではありません。

最近こそは、人前で話をする機会も多く、だいぶ話すこと自体には慣れてきたのですが、まだまだ要領よく順番に説明する事には苦労しています。
最近読んだ育児書にも、小さな頃からこのロジカル・シンキングを育てることはコミュニケーションをとる上で、抵抗なくスムーズにできる方法の一つだと書いてありました。

その第一歩は、とにかく子どもに話をさせる機会を多く持たせることだそうです。言葉を、子どもから奪わないことだそうです。
例えば、子どもが親に何かを話したい時「忙しいから後でね。」なんて言っていませんか?
例えば、子どもが質問をされたのに親の方が先回りをして、子どもの名前や年などを先に言ってませんか?

自由に話をさせたり説明をさせたりすることで子どもは言葉を学んでいるのです。その学ぶ機会を親が奪っていることも多いようですね。
そして、単語で言葉を返すよりも、親もたくさんの言葉をそえて話しかけることが子どもの語彙を広げ、想像力も働くようになるそうです。
 「りんごが美味しそうだね。」と言うよりも「赤くてきれいなりんごだね。きっと、食べると甘くて美味しいだろうね。」という方が子どもの頭にはイメージがはっきりとできるのです。
「りんごが美味しそうだね。」と言うよりも「赤くてきれいなりんごだね。きっと、食べると甘くて美味しいだろうね。」という方が子どもの頭にはイメージがはっきりとできるのです。その積み重ねが、ロジカル・シンキングができるようになるのだそうです。そして、話す事が好きになり物事を理解することも早くなるのだそうですよ。

そして、大人にとっても誰かに話すことはストレス解消にも心のリハビリにもなるそうです。
そうですよね!!話すだけでも気分がすっきりとなること多いですもの。
 私もいっぱい話す事にしようっと!!(話しすぎってか?
私もいっぱい話す事にしようっと!!(話しすぎってか? )
)
2007年06月21日
いい褒め方。悪い褒め方。
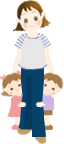
子どもの褒め方にもいい褒め方と悪い褒め方があるというのを知っていましたか?

子どもを褒めて子育てをすることは、どの親も理想です。どの育児書にも褒めて育てるとよい子どもになると書いてあるから、その言葉だけを取ると何をするにも褒める事は、子どもを正しい方向に導くことになるのだと思い込んでしまいがちになります。
しかし、子どもにとって褒められた時、それがプレッシャーになる褒められ方なら、子どもの心には違う変化が起きるということも知っておく必要もあるのです。
ハイム・G・ギノット著「子どもの話にどんな返事をしていますか?」の本の中でこうありました。
褒めることは薬の投与と同じで、ルールと注意を必要とする。もっとも重要なルールは、褒める対象は子どもの努力や成果であって、性格や人格ではないということ。
例えば、子どもが一生懸命に自分の部屋の掃除をしてきれいにした時、子どもの頑張りや部屋がきれいになったことを褒めるのはとても自然なことなのですが、子どもに「あなたはとてもいい子だ」とか「あなたはいつも素直でおりこうだね」などの褒め言葉はよくないそうです。
子どもが、自分はそんなにいい子ではないと思っているなら、この言葉はいつもいい子でいなければならないという重いプレッシャーを感じるかもしれないのです。そして、今度はいい子じゃないと暴露されることに不安を抱くかもしれないというのです。
子どもは、性格を直接ほめられることは直射日光を浴びるようでまぶしくて不快に感じるものです。

人は褒められると当惑します。(褒め殺しってこともあるし・・・)あまりにも褒められすぎるとその一部でも否定せずにはいられない気持ちになります。
子どもならなおの事、「自分は素直で素晴らしい人間だ」と言える子はいないのです。
いい子ね。いい子ね。っていわれ続けた子が突然、爆発してしまうことはよく聞きます。ずうっと、自分はいい子でいなければならないと強迫観念にとらわれて本当の自分が出せないまま、空気を入れ続けられて破裂してしまう風船のように・・・。そうならない為にも、褒めることを知っていなければと思います。
褒める事は、2つのプロセスから成り立っていて、私たちが子どもに言うことと、子どもがそれを聞いて自分自身に言うことなのだそうです。
褒める時は子どもがしたこと(努力・手伝い・仕事・心遣い・想像・達成など)の何を私たちが気に入り、評価しているのかをはっきり言うことであり、私たちの言葉が子どもにとって肯定的な自己イメージを与える魔法の言葉であることなのです。
言葉には、人を傷つけたり慰めたり、勇気づけたりする力があります。心を乗せた本当の言葉なら、子どももしっかりと受け取ってくれます。そんな褒め言葉をたくさん使ってあげたいものですね!!

2007年06月16日
個性とわがまま
昨夜、久し振りに短大の頃の友達からの電話がありました。彼女は今、山口の小学校で教諭をしているとのこと。いろいろと久し振りに話すうちに、小学校の子どもの話をはじめました。
ある子どもが転校をしてきた時の話です。母親に連れられて、職員室に入って来ました。
彼女は生徒にここに座りなさいと軽く言った時に、その子の親がこう言ったそうです。「そういう強制はやめて欲しい」と。「うちの子はきょろきょろするのが個性なのだから無理強いはしないでほしい」と言われたそうです。
私の友達もそんなことを言われたのは、初めてでどう対応をしていいかわからず、それでもとにかく座らせて担当の先生に代わったのだそうです。彼女は、とても寂しい思いをしたようでした。ひとしきり私に話すと満足したのか話題は変わりましたが私もやるせない気持ちになりました。
「個性」とは何でしょうか?確かに人と違う性質を持っていることを個性と言います。でも、椅子に座らなくてきょろきょろすることは「個性」とは言わないのです。言うとすれば「野生」でしょう。
好きな事だけして嫌いな事をしないと言うのは何も努力しない。その子は、我慢して座ると言う事を言われないまま、きたのでしょうか。そして、これからもすべてのわがままを「個性」で片付けてしまうのは恐ろしいことです。
わがままにしたいだけさせることは、個性とは大きくかけ離れているような気がします。今は、物や食べ物も豊かで、好きな事もできるようになりました。その中でいかに自分をコントロールできるかをもっと子ども達に大人が教えていかなければと思います。 ちょっと、今日は考えさせられました。
彼女とはまた再会を約束して、電話を切りました。山口でふぐ鍋でも囲んで、いろんなこと話しができればいいなあ~!


ある子どもが転校をしてきた時の話です。母親に連れられて、職員室に入って来ました。
彼女は生徒にここに座りなさいと軽く言った時に、その子の親がこう言ったそうです。「そういう強制はやめて欲しい」と。「うちの子はきょろきょろするのが個性なのだから無理強いはしないでほしい」と言われたそうです。

私の友達もそんなことを言われたのは、初めてでどう対応をしていいかわからず、それでもとにかく座らせて担当の先生に代わったのだそうです。彼女は、とても寂しい思いをしたようでした。ひとしきり私に話すと満足したのか話題は変わりましたが私もやるせない気持ちになりました。

「個性」とは何でしょうか?確かに人と違う性質を持っていることを個性と言います。でも、椅子に座らなくてきょろきょろすることは「個性」とは言わないのです。言うとすれば「野生」でしょう。
好きな事だけして嫌いな事をしないと言うのは何も努力しない。その子は、我慢して座ると言う事を言われないまま、きたのでしょうか。そして、これからもすべてのわがままを「個性」で片付けてしまうのは恐ろしいことです。

わがままにしたいだけさせることは、個性とは大きくかけ離れているような気がします。今は、物や食べ物も豊かで、好きな事もできるようになりました。その中でいかに自分をコントロールできるかをもっと子ども達に大人が教えていかなければと思います。 ちょっと、今日は考えさせられました。

彼女とはまた再会を約束して、電話を切りました。山口でふぐ鍋でも囲んで、いろんなこと話しができればいいなあ~!


2007年06月09日
失敗は成功のもと!

自分のお子さんが「引っ込み思案」で悩んでいるお母さんは、少なくないようです。
私の周りにも、子どもが自分から行動を起こさない事に不満を持っているお母さんは結構います。よく、どんなに励ましても叱っても、自分からはいかないと言う声も聞きます。
でも、どんなに励ましても叱っても子どもの引っ込み思案は直らないと思うのです。
なぜなら、引っ込み思案になった原因を取り除かなければ子どもの気持ちは前に進まないと思うからです。
私が思うのは、引っ込み思案の子どもは、やる気持ちがないのではなく失敗することを恐れているのではないかと思うのです。やる気持ちはあっても、先読みをしてしまいそれを行動に移せないのが実状なのかもしれません。
これをやると叱られてしまうかもしれないとか、こうすると失敗してしまうのではないかと、失敗するぐらいなら何もしない方がいいというブレーキを心にかけてしまう子どもが多いのかもしれません。
まず、引っ込み思案を直すには「失敗はしてもいいのだ」と教えることから始めることだと思います。
例えば、自分の失敗談から、そこから得たものがあることを話してあげることでもいいと思います。身近な人の失敗は、誰にでも失敗はあるんだと子どもに安心感を与えます。
人間は失敗を重ねながら生きています。私たちは失敗しながらそこから学び考え創造することをしています。
子どもにも、失敗する価値をを教えてあげられれば、次第に失敗する事を恐れずに前向きに物事を考える力ができてくると私は思います。
失敗は成功のもと
何て素晴らしいことわざだと思いませんか!!

2007年06月06日
子どもと嘘

子どもがウソをついた時、ドキッとしたことありますか?それで頭ごなしに叱ったりしたことないでしょうか?
子どものウソは現実と願望が一緒になりウソをついてしまうことがあるようです。それから、子どもがウソをつくとき、周りに何かを求めている事が多く、特に親に対しては自分をいい子に見せたいという気持ちから出てしまうこともあります。
もし、子どもが他の人に迷惑をかけたり、悪者にしようとするウソなら、先ずは相手がそのウソのためにどんなに傷ついたか、ウソをつかれた心の痛みをわからせるように教えてやらなければいけないと思います。
ただ、ウソはいけないと言う事でなく、ウソをつくことで傷つく相手のことを思いやれるようにいい聞かせることが大事なのです。
ウソには、「ウソも方便」ということわざもあるぐらい、時にはウソをつくことで相手を傷つけないこともあります。

いつか、私がご近所のお年寄りから、手作りのおはぎを貰った事がありました。持って帰り、子ども達と食べたのですが、あまり味がなく正直に言うと子どもにとってはとても美味しいものとは言えなかったようです。次の日、子どもと一緒の時に、そのお年寄りとお会いしました。そこで、おはぎのお礼と美味しかったですよっと伝えたのでした。後で、家に戻って子どもに聞かれました。

「何故、あんまり美味しくなかったのに、美味しいと言うの?それは、ウソつくことにならないの?」って。
確かに、美味しくないものを美味しいと言うことは、ウソかもしれません。そこで子どもに質問をしてみました。「もし私が美味しくないって言ったら、おばあちゃんはどんな気持ちがするかな?」と聞くと「嫌な気持ち」と答えました。
「嫌な気持ちにさせるなら、言わない方がいいよね。おばあちゃんが、美味しいと言って、喜んでくれるならその方がいいもんね。」
そう言うと、にっこりと笑って遊びに行ってしまいました。
相手の気持ちを考えて、それで終わるならそれはそれでいいと思うのです。それが、人付き合いでもあるのですから。
大人は、ある意味嘘つきです。社交辞令は数知れずあります。来て欲しくなくてもどうぞと言ったり、腹が立っているのに、ごめんなさいと言われて許したり、全てが全て正直には言えないのです。
そんなことを思うと、子どものウソって、まだかわいらしいと思いませんか?
私は、周りにダイエットを宣言して未だにやってません。。。
 これって、やっぱり「うそつき~~~っ」て言われるのかなあ??? いいえ、実行してないだけですよお。。。。(苦笑・・・
これって、やっぱり「うそつき~~~っ」て言われるのかなあ??? いいえ、実行してないだけですよお。。。。(苦笑・・・ )
)
2007年05月31日
子ども同士のけんか
私には、姉が2人に弟が2人います。それこそ、子どもの頃はつまらない事でけんかをよくしたものです。
我が家の子ども達を見ていても、どっちが先に手を出したとかお風呂掃除は誰がするのかとか、小さな事でよく言い争いをしたり、時にはたたいたりと毎日泣いたり怒ったりしています。
しかし、この子どもの頃の喧嘩は、実は成長する上でとても大きな意味を持つものだそうです。
それは、子どもは喧嘩をしながら、それぞれの年齢に応じた解決策を見つけようとしているのです。つまり、子どもなりに頭を使いながら妥協点を見出すことによって、それなりに社会性や協調性を身につけていくというわけです。
喧嘩は自分の要求がすべて通るのではなく、自分とは意見の違う相手もいるし、妥協するということを発見する絶好のチャンスでもあるのです。子ども同士が喧嘩を始めたら、怪我をしないように見守りながらある程度させるのも心理的な発達の過程で必要なことだと思います。
最近の凶悪な未成年による事件は、子どもの社会性の欠如が原因の一つであり、子ども同士の喧嘩が少なくなったこととは無関係ではないように感じます。
子ども同志が困難な状況を切り抜ける体験をすることによって、相手の気持ちにも気づき、また自立心も育つのではないかと思うのです。
喧嘩をしながら、相手のことがわかり妥協しあいながらお互いの気持ちに気づかせてくれる。子どもの頃の喧嘩も貴重な体験なのです。




我が家の子ども達を見ていても、どっちが先に手を出したとかお風呂掃除は誰がするのかとか、小さな事でよく言い争いをしたり、時にはたたいたりと毎日泣いたり怒ったりしています。
しかし、この子どもの頃の喧嘩は、実は成長する上でとても大きな意味を持つものだそうです。

それは、子どもは喧嘩をしながら、それぞれの年齢に応じた解決策を見つけようとしているのです。つまり、子どもなりに頭を使いながら妥協点を見出すことによって、それなりに社会性や協調性を身につけていくというわけです。
喧嘩は自分の要求がすべて通るのではなく、自分とは意見の違う相手もいるし、妥協するということを発見する絶好のチャンスでもあるのです。子ども同士が喧嘩を始めたら、怪我をしないように見守りながらある程度させるのも心理的な発達の過程で必要なことだと思います。
最近の凶悪な未成年による事件は、子どもの社会性の欠如が原因の一つであり、子ども同士の喧嘩が少なくなったこととは無関係ではないように感じます。
子ども同志が困難な状況を切り抜ける体験をすることによって、相手の気持ちにも気づき、また自立心も育つのではないかと思うのです。
喧嘩をしながら、相手のことがわかり妥協しあいながらお互いの気持ちに気づかせてくれる。子どもの頃の喧嘩も貴重な体験なのです。